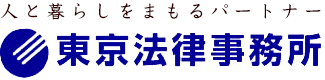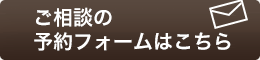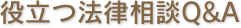相続土地国庫帰属制度の創設
父が亡くなり、遺産に実家の土地建物と別荘地に更地があります。別荘地の更地は相続人の誰も取得を希望していません。何か良い手段はないでしょうか?
回答者: 司法書士 半田久之
相続登記の申請義務化など所有者不明土地問題解決のための法改正にあわせて、2023年4月に相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。この制度の利用を検討してはどうでしょうか?
以下では、簡単にこの制度についてご説明します。
この制度は、相続した土地で一定の条件を満たすものについて、国(法務局)に対して承認申請を行い、承認された場合には、10年分相当の管理費用(20万円~)を国に納付し、国所有にしてもらうというものです。
では、誰が、どのような土地を申請できるかを以下で見ていきましょう。
まず、申請ができるのは、相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地を取得した相続人です(相続土地国庫帰属法第2条第1項)。売買により取得した方は対象となりません。
次に、対象土地が以下にあてはまる場合は、承認申請そのものができません(同条第3項)。
さらに、承認申請は行えたとしても、対象土地が以下にあてはまる場合は、国は、対象土地を国所有とすることを不承認にしなければならないとされています(同法第5条第1項)。
例:他の土地に囲まれて公道に通じない土地で現に民法上の通行が妨げられている土地など
例:災害の危険により、土地や土地の周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地など
申請後、法務局担当者による書面審査、さらに土地の実地調査を行うことが予定されており(同法第6条)、結果がでるまでの標準処理期間は8か月とされています。
以上が相続土地国庫帰属制度の概要です。
なお、2024年3月31日現在の統計によれば、制度開始後、1,905件の承認申請がなされ、そのうち承認248件、却下6件、取り下げ213件となっています。承認件数はまだ少ないですが、今後、さらに審査が進めば、まだ結果が出ていない申請についても結果が出されるものと思います。
(2024年4月記)
「相続土地国庫帰属制度」に関する取扱事件
- →相続