労働組合顧問弁護士としての主な活動は、次のとおりです。
- ①労働組合執行部からの、組合の組織運営、組合活動、会社への要求事項、会社からの提案への対応、個別組合員の事案などの相談に迅速に対応して、面談・メール・電話で回答します。
- ②相談への回答のほかに必要がある場合は、労働組合として有効に利用してもらうため、労働組合からの依頼により弁護士としての法律意見書などの書面を作成します。
- ③執行委員会や組合集会等における学習会・研修会の講師として、労働法や職場で問題になっている事項などをテーマに講演を行います。
- ④労働組合向けに役立つ法律情報などを提供します。
- ⑤相談のほか、労働組合からの依頼により事件を受任し、交渉や訴訟、労働委員会手続などの弁護士活動を行います。
- ⑥単位労働組合の場合は、組合員サービスとして、組合員からの面談法律相談に、初回相談料は無料で対応します。
相談事項は、民事(不動産・相続・離婚・交通事故その他)、刑事、労働など何でも相談可能です。秘密厳守のため、組合員からの相談内容を組合執行部へお知らせすることはありません。
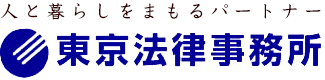
 03-3355-0611
03-3355-0611



















